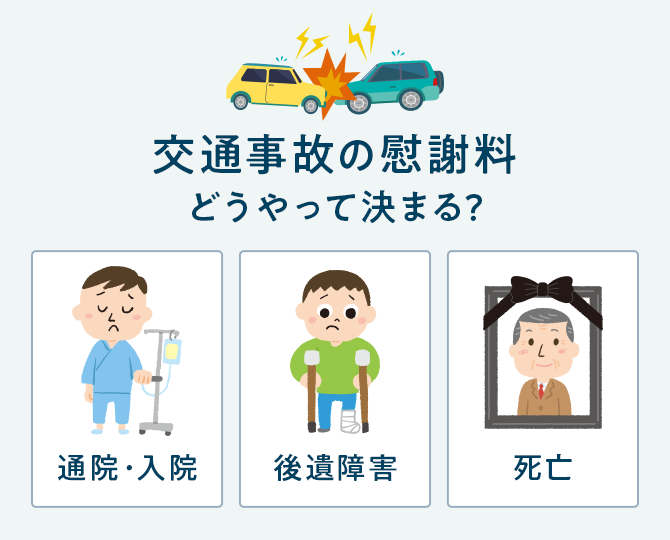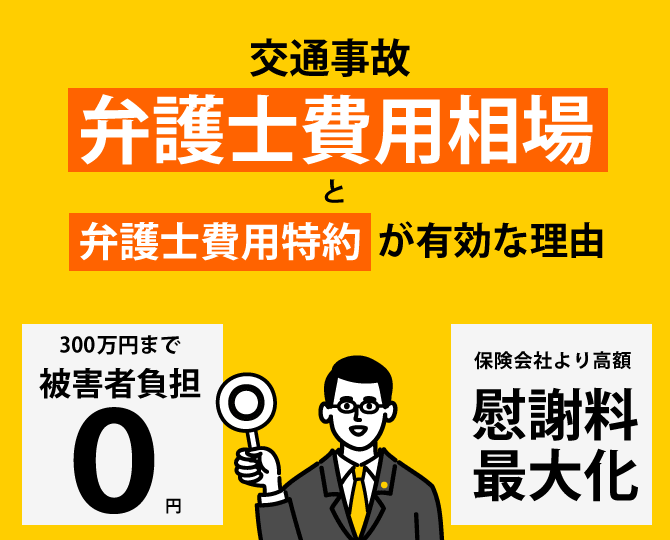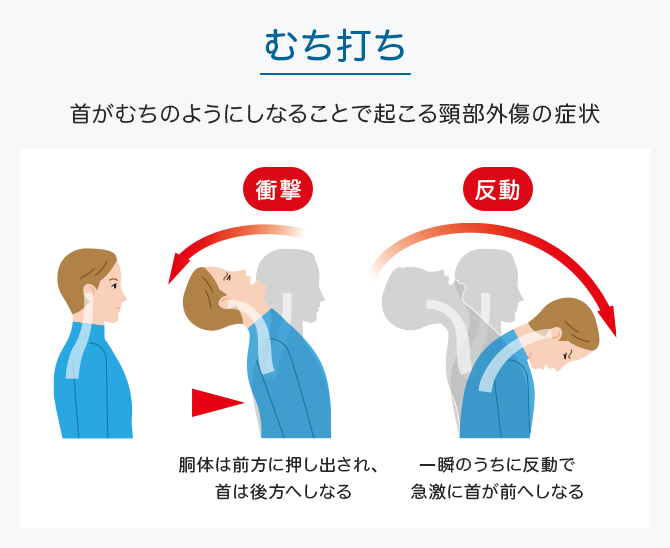交通事故を起こした相手が未成年だった場合、親に損害賠償請求は可能?
- 監修記事
-

交通事故弁護士相談広場編集部

目次[非表示]
未成年者でも交通事故を起こすと「不法行為責任」が発生することがある
現在の民法では、20歳未満の人が「未成年者」とされています。(民法改正により、令和4年(2022年)4月1日からは、18歳で成年となるため、18歳未満の人が「未成年者」となります)。未成年者は判断能力が不十分なため、原則として、契約をひとりで結ぶことはできません。
未成年者については、ひとりで契約を結べるかという問題と並んで、交通事故を起こしたら「不法行為責任」を負うかという問題があります。交通事故は故意や過失によって引き起こされ、被害者に損害を発生させる「不法行為」(民法709条)の一種だからです。
未成年者の場合、判断能力が不十分であることを理由に、不法行為責任が発生しないケースがあります。未成年者が不法行為責任を負うには、本人に「責任能力」が必要と定められているからです。(民法712条)
責任能力とは、判断能力を不法行為に当てはめたものであり、「自分の行為で損害が生じたら、これを償わなければならない」ということを理解できる力のことです。こうした理解ができるにもかかわらず、損害を生じさせてしまったからこそ、それを償わせることができるわけです。
交通事故の相手が未成年者の場合、責任能力があれば未成年者本人に対して損害賠償請求ができます。責任能力がなければ、未成年者本人に対して損害賠償請求はできないことになります。
未成年者自身に損害賠償請求できる場合とは?
未成年者が引き起こした不法行為について、本人に責任能力があるとして損害賠償請求ができるのは、具体的にどのようなケースなのでしょうか?
未成年者に責任能力がある場合
未成年者に責任能力があるかどうかは、
- 未成年者それぞれの知的レベル
- 未成年者が行った行為の内容
の2つを基に、ケースバイケースで決められます。
12歳くらい以上の知的レベルがあると、損害賠償責任が生じやすくなる
①の未成年者それぞれの知的レベルに関しては、小学校を卒業する頃(年齢でいえば12歳くらい)の知的レベルがあれば責任能力を認めてよいというのが裁判例の傾向です。小学校での教育も含め、人間の精神の発達をたどれば、このくらいの年齢になれば、自分がしてしまったことの責任を自覚できるであろうというわけです。
この考え方によれば、交通事故を起こした未成年者が12歳くらい以上であれば、未成年者本人に損害賠償責任が生じやすくなります。(「生じます」と断定しないのは、責任能力の認定には上記②も関係してくるからです。)
交通事故を起こしたのが中学生、高校生、20歳未満の大学生や社会人であれば、いずれも立派な責任能力者として、未成年者自身が損害賠償責任を負うことが多くなります。
なお、小中学生が起こす交通事故として多いのは、自転車走行中に歩行者とぶつかり、死傷させてしまうケースです。
未成年者に責任能力がない場合
反対に、12歳くらいにならない未成年者の場合、責任能力が認められにくくなります。
また、事故を起こした未成年者の年齢が12歳くらい以上であっても、知的障害などにより、12歳くらいの知的レベルになければ、責任能力が認められにくくなります。
これらの場合、未成年者本人に対しては、その責任能力がないことを理由に、交通事故で発生した損害賠償請求をすることができません。
未成年者の交通事故に対する親の監督者責任
交通事故においては、車が壊れるなどの物的損害、怪我をすることによる身体的・精神的損害、治療費その他の金銭的損害が生じます。このとき、事故を起こしたのが責任能力のない未成年者だから損害賠償を請求できないといわれても、被害者としては、心情的にとても納得できるものではありません。
被害者としては、「未成年者なら親の監督のもとにあるはずだ」「未成年者に責任がないのなら親に責任を取ってもらおう」と考えるのが普通です。
そこで、未成年者が交通事故を起こしたときの親の責任についてみていきましょう。
監督者責任(民法714条)とは
未成年者が交通事故を起こし、責任能力がないことを理由に未成年者自身は損害賠償をしなくてもよいとされた場合、その未成年者を監督する法律上の義務のある者が損害賠償をしなければなりません(民法714条)。これを監督者責任といいます。
未成年者への監督義務者は、親権者である父母です(民法820条、818条1項)。父母が亡くなるなどして親権者がいないときは、父母が指定し、または家庭裁判所が選任した未成年後見人が監督義務者となります(民法857条本文、838条1号)。その他、未成年者が入所している児童福祉施設の長が監督義務者になることもあります(児童福祉法47条1項本文)。
親権者などが監督義務を尽くしたとき、あるいは監督義務を尽くさなくても交通事故が起きたといえるときは、親権者などの監督義務者は損害賠償をしなくてよいとされています(民法714条1項但書き)。ただ、監督義務を尽くしたことなどは監督義務者自身で証明しなければならず、こうした証明は実際にはとても難しいといわれています。
責任能力のない未成年者が起こした交通事故については、父母などの監督義務者が損害賠償をしなければならなくなるのが普通と考えてよいでしょう。
親の監督者責任(民法714条)は何歳の子どもまで?
それでは、親などの監督義務者が損害を賠償をしなければならなくなるのは、未成年者が何歳までの場合なのでしょうか。
さきほど、小学校を卒業する頃(年齢でいえば12歳くらい)の知的レベルがあれば責任能力が認められやすいのが裁判例の傾向であるとお話ししました。
この基準を監督者責任と結びつけると、未成年者が12歳くらいよりも前であれば、責任能力が認められにくいため、未成年者が起こした交通事故については、親などの監督義務者が損害を賠償しなければならないことが多くなります。
ちなみに、未成年者が起こす交通事故のパターンとしては、小中学生なら自転車で歩行者とぶつかる事故、高校生なら自転車で歩行者とぶつかったり、バイクで歩行者や他の車両とぶつかる事故が考えられます。大学生や社会人になると、さらに自動車での事故が加わってきます。
親が負う監督者責任以外の責任とは?
運転免許を取れる年齢を見ると、原付免許は16歳以上、普通自動免許は18歳以上と、責任能力の目安となる年齢を過ぎています。未成年者が原付や自動車で事故を起こした場合、その子が知的障害などでない限り、親は監督者責任を負いにくくなります。その場合、親は、未成年者である子どもが起こした事故について、一切の責任を負わなくてよいのでしょうか?
親自身に不法行為が成立する可能性がある
子どもに責任能力があることで親が監督者責任を負わない場合でも、親が法律上の監督義務(民法820条)を果たさなかったことと、子どもが交通事故を起こしたこととの間に相当因果関係があるといえるときは、親自身の不法行為となり(民法709条)、被害者は親に対して損害賠償を請求できるというのが判例です(最高裁判決昭和49年3月22日)。
「相当因果関係」とは、「Aという行為をすればBという結果が生ずるのが当たり前」といえるAとBの関係をいいます。
たとえば、子どもが無免許で親の車を乗り回しているのを知っていながら、子どもに注意するわけでもなく、車のカギを放置していたため、子どもが簡単に乗り出せた親の車で事故を起こした場合、子どもの無免許運転に対する親の監督義務違反と子どもの起こした交通事故との間には、「こうした親の監督態度では、子どもが事故を起こしても当たり前」といえる関係、つまり相当因果関係が認められます。
このような親自身の不法行為責任を認める背景には、責任能力のある子どもに損害賠償責任を認めても、年端のいかない子どもでは賠償責任を果たすだけのお金がないのが普通で、被害者は泣き寝入りせざるを得ないという事情があります。
監督者責任と一般の不法行為責任の違い
子どもの起こした交通事故について、親が監督者責任を負う場合と一般不法行為責任を負う場合とでは、監督義務の証明についての違いがあります。
監督者責任では監督義務を怠らなかったことを親が証明する
監督者責任の場合、親の側で、自分が監督義務を怠らなかったことを証明しなければなりません。証明できれば、監督者責任を免れます。証明できなければ、監督者責任が生じます(民法714条1項但書き)。そして、実際にはこうした証明がとても難しいことは、前にお話ししたとおりです。
一般不法行為では親の監督義務違反を被害者が証明する
一般の不法行為責任の場合には、被害者の側で、親が監督義務を果たさなかったことを証明しなければなりません。証明できれば、親が損害賠償責任を負います。証明できなければ、親は損害賠償責任を負いません(民法709条)。
親が「運行供用者責任」を追及されるケース
未成年者が、親の自動車やバイクに乗って人身事故を起こした場合、被害者は、その自動車やバイクの所有者である親に対して損害賠償を請求することができます。この場合の親は、自動車損害賠償保障法(略して「自賠法」)3条に定められた「運行供用者」に当たるからです。
「運行供用者」とは、自賠法3条に出てくる「自己のために自動車を運行の用に供する者」を略したことばです。「運行」とは、自動車やバイクを走らせることをいいます。
判例(最高裁判決昭和43年9月24日)は、運行供用者といえるには、
- 自動車の運行を支配していること(運行支配)
- 自動車の運行から利益を得ていること(運行利益)
の2つが必要であるとしています。
「運行支配」とは、自動車を走らせるか走らせないかを自分の意思でコントロールできることをいい、「運行利益」とは、運行が自分のために行われていることを指します。
親は、自分の自動車について、子どもに乗らせるか乗らせないかを決めることができます。子どもが親の自動車を運転できるのは、親が子どもに乗らせると決めたからです。たとえ子どもが運転中であっても、その自動車の運行支配は親が握っているととらえることができます。
また、親から借りた自動車を運転する子どもは、親の自動車をぶつけたり汚したりしないように運転するのが普通であり、広く考えれば、子どもによる運転は親のために行われているといえます。
こうして、親の自動車を子どもが運転している間も親は運行供用者であり続けるのであり、その間に起こした子どもの人身事故について、自賠法3条により、親が運行供用者としての損害賠償責任を負うことになるわけです。
運行供用者でも損害賠償を免責されるケース
親は、自分の自動車を子どもが運転することについて、次の3つすべてを証明すれば、損害賠償責任を免れることができます(自賠法3条但書き)。
- 親と子どもの両方が自動車の運転について注意を怠らなかったこと(親は常に子どもに対して運転上の注意点を厳しく戒め、子どもも交通ルールを完ぺきに守って運転していた場合など)
- 被害者または運転者以外の第三者に故意または過失があったこと(被害者車両がセンターラインをオーバーしたため未成年者車両とぶつかった場合など)
- 自動車の構造上の欠陥または機能の障害がなかったこと(ブレーキの故障、タイヤのパンクなどがなかったこと)
子どもによる無断運転では親の容認の有無が決め手に
これまでの話は、親の同意のもとで子どもが親の自動車を運転したケースでしたが、無断で親の自動車を運転して事故を起こした場合、親の運行供用者としての責任は生じるのでしょうか。
要は、親の自動車を運転することについての親の容認態度が決め手といえるでしょう。
親が自動車のキーを放ったらかして、子どもが自由に乗れるような状況を作り出していたのであれば、親の運行支配が子どもに及び、子どもの運転による運行利益を親が得ているといえます。子どもが起こした事故に対し、親の運行供用者としての責任が生じることになります。
一方、親が自動車のキーを勝手に持ち出せないように厳重に管理していたにもかかわらず、子どもが強引にキーを持ち出して自動車を運転した場合、子どもは親の意思に反して自動車を運転したわけですから、親の運行支配が子どもに及ぶと見るのは難しいでしょう。子どもが起こした事故について、親の運行供用者としての責任は生じないと考えるべきです。
未成年者が交通事故を起こした場合の示談の相手
ここからは未成年者が交通事故を起こしたとき、誰と示談交渉を進めていけばよいのかについて見ていきます。
保険に入っているなら示談交渉の相手は保険会社になる
これまで未成年者が交通事故を起こしたとき、「誰に損害賠償責任が発生するのか」を検討してきました。交通事故では不法行為責任あるいは運行供用者責任が未成年者本人や親に発生する場合を説明しました。
事故の相手としては、多くの場合、親や未成年者本人と示談交渉をする必要はありません。なぜなら多くの車には「任意保険」が掛けられているからです。未成年者が運転する車に任意保険の「対物賠償責任保険」「対人賠償責任保険」が掛けられていれば、その車が起こした事故についてはそれらの保険が適用されるため、示談交渉の相手は保険会社となります。決まった示談金も保険会社が支払うので「払ってもらえない」という事態にはなりません。
任意保険が適用されるなら、親に監督者責任や運行供用者責任が発生するかどうかに関係なく、保険会社が乗り出して、通常の交通事故と同じ処理がなされます。
任意保険が適用されなければ本人や親と交渉
未成年者が加害者の場合、任意保険が適用されないケースがあります。それは以下のような場合です。
- 未成年者が故意に事故を起こした場合
- 地震、津波、台風、洪水などの天変地異によって事故が起こった場合
- 保険に年齢制限がつけられていて未成年者が適用外となっている場合
上記のようなケースでは、親の自動車に任意保険が掛けられていても、親の自動車で未成年者が起こした交通事故に保険が適用されません。保険会社は示談交渉に乗り出してはくれないので、被害者は、未成年者や親に直接損害賠償請求するしかありません。
なお、未成年者が無免許運転や飲酒運転をしていた場合などでも、上記のケースに該当しなければ、対人賠償責任保険・対物賠償責任保険が適用されます。加害者の免許取得や飲酒の有無によって被害者救済に差をつけるべきではないからです。
無保険の場合も本人や親と交渉
未成年者が起こした交通事故に任意保険が適用されるためには、未成年者が運転する車に任意保険が掛けられていなければなりません。未成年者の車両が無保険であれば、その車が起こした事故には任意保険の適用がないため、保険会社は示談を代行してくれません。被害者は、加害者である未成年者やその親と直接に示談交渉をして、賠償金を支払わせるしかありません。
未成年者が無保険で事故を起こした場合に生じる問題
未成年者が無保険で交通事故を起こした場合や事情により任意保険が適用されない場合には、以下のような問題が発生します。
示談に応じない
任意保険が適用される場合、保険会社が示談交渉に応じますし決まった示談金を支払ってもくれます。しかし加害車両が無保険の場合、運転者が示談交渉に応じないで逃げてしまうケースが多々あります。特に運転者が未成年者の場合、事故を軽く考えたり怖くなったりして対応しない例が数多くみられます。そうなると、被害者は誰にも損害賠償してもらえないという苦しい立場に立たされます。
支払能力がない
未成年者は、示談交渉から逃げないとしても、若年で収入も乏しいことから、支払い能力がないケースが多数あります。被害者に後遺障害が残った場合などには損害賠償金も高額になりますが、未成年者にそれを支払えるだけの資力がなかったら、結局損害賠償は受けられません。親が監督者責任を負う場合や、監督者責任は負わないけれども任意で肩代わりしてくれる場合であれば良いのですが、そのようなケースでない限り、被害者が泣き寝入りせざるを得ないのが実状です。
未成年者が相手の場合の損害賠償金計算方法
未成年者が交通事故を起こしたとき、損害賠償金はどのようにして計算されるのか、どのくらいの賠償金を請求できるのか気になる方もおられるでしょう。
相手が未成年者であっても、損害賠償金の計算方法は通常の交通事故と同じです。
車が破損したら修理費用や買い換え費用、諸経費などを請求できます。怪我をしたら治療費や雑費(診断書料金など)、交通費、休業損害、慰謝料などが請求の対象になります。後遺障害が残ったら後遺障害慰謝料や逸失利益、死亡したら死亡慰謝料や死亡逸失利益を請求することができます。
こちらも読まれています交通死亡事故の慰謝料はどのくらい?残された遺族ができることは? 交通事故の損害賠償請求を行う権利があるのは原則として被害者本人のみだが、被害者が死亡してしまった事故でも、被害者の遺族が...この記事を読む
過失割合の決まり方も通常の交通事故と同じです。未成年者だからといって、過失割合を高くされたり低くされたりすることはありません。
加害者が未成年者であっても損害賠償金を減らされることはないので、その点は安心です。ただ、法的に請求権があってもそれを相手が支払えないことが問題なのです。
相手が未成年者で賠償金を支払えない場合の対処方法
もしも交通事故の加害者が未成年者で、賠償金を満足に支払えない場合、どのように対応すれば良いのでしょうか?
任意保険適用なら保険会社に請求
任意保険が適用される場合には、迷わず保険会社に損害賠償請求をしましょう。相手が未成年者で、きちんと親や保険会社に事故を報告していない様子であれば、相手に催促をして早急に保険の手続を進めさせましょう。
保険不適用で本人無資力なら親への請求を検討
保険が適用されない場合で未成年者本人に支払い能力がなさそうであれば、親に監督者責任や一般の不法行為責任が発生しないか検討します。これらのうち、どちらかの責任が発生すれば、親に対して全額の損害賠償請求が可能となります。
子どもが起こした交通事故について親が負う損害賠償責任をまとめると、次のようになります。
- 未成年者が12歳頃より前の年齢であれば「監督者責任」が生じやすい
- 未成年者が12歳頃より後の年齢であれば「一般の不法行為責任」が生じやすい
- 車の所有名義人が親であれば「運行供用者責任」
他人の車での事故なら車の所有者に請求
未成年者が他人名義の車で事故を起こした場合、被害者は、車の所有者に対して損害賠償請求をすることができます。車の所有者は、車への「運行支配」を手にし、車を走行することによる「運行利益」を得る点で「運行供用者」ということができ、車が起こした人身事故に対する損害賠償責任を負う立場にあるからです(自賠法3条本文)。
車の所有者が親であれば親に損害賠償請求できますし、友人の車なら友人、会社の車なら会社、知人の車なら知人に損害賠償請求をすることができます。
未成年者が運転していたのが勤務先会社の車で、その車に任意保険が掛けられていれば、保険が適用されてるため、保険会社と示談交渉を進めていくことが可能です。
未成年を使用する者に請求
交通事故を起こしたのが会社の従業員だと、従業員を雇用している会社に損害賠償責任が発生する場合があります。これを「使用者責任」と言いいます(民法715条)。
使用者責任は、被用者が業務の執行について行った不法行為に対し、雇用主が損害賠償責任を負うというものです。
たとえば、未成年者がある会社でアルバイトをしており、仕事の一環で車を運転して事故を起こした場合、被害者は会社に対し、会社の使用者責任を理由に損害賠償請求ができることがあります。
使用者責任の場合、車の名義人が会社である必要はなく、未成年者本人や親名義の車でも、業務の執行について走行中の事故であれば、会社の使用者責任が発生します。
使用者責任が生ずるのは「業務執行についての交通事故」が対象なので、従業員が起こした仕事と全く関係のないプライベートな事故について使用者責任が生じないのはもちろんです。
自賠責保険に請求
未成年者の車に任意保険が掛けられていない場合であっても、自動車損害賠償責任保険(略して「自賠責保険」)は掛けられているはずです。自賠責保険が掛けられていない自動車を運転することは法律で禁止されており(自賠法5条)、これに違反すると1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられるからです(自賠法86条の3 1号)。
自賠責保険の掛けられた車により被害を受けた場合、被害者は自賠責保険から賠償を受けられます。たとえば、被害者が死亡すれば3,000万円、傷害を受けたら120万円というように、被害の程度に応じた保険金額が政令で定められています。
ただ、自賠責保険が適用されるのは、死亡や傷害といった人身事故のケースのみで、物損事故には適用されません(自賠法1条)。また、自賠責保険で支払われる保険金の金額はかなり低額であり、事故の損害すべてをカバーすることはできません。足りない分は、未成年者や親など、損害賠償責任を負う者自身に請求するしかありません。
政府による保障事業を利用
稀に、自賠責保険さえ掛けられていない車もあります。こうした車によって被害を受けたら、自賠法が定める「政府の自動車損害賠償保障事業」を活用しましょう。
この事業は、自賠責保険が掛けられていない車により被害を受けた場合や、ひき逃げなど加害者が不明である場合に、政府が、政令で定める金額を被害者に支払うことにより損害をカバーしようという制度です(自賠法72条1項)。
被害者は、国が指定した損害保険会社の全国にある支店窓口で保障事業の申請をすることができます。申請がパスすれば、申請した保険会社により、政令に定められた金額が支払われます。保険会社は、自ら支払った金額を政府に対して請求します。
「政府の自動車損害賠償保障事業」については、国土交通省のWEBサイトで詳しい解説がされていますので、ご参照ください。
参考リンク:国土交通省WEBサイト「政府保障事業について(ひき逃げ・無保険事故の被害者の救済)」
未成年者が相手の事故に遭ったら弁護士に相談を
交通事故の相手が未成年者でも、保険が適用されれば、被害回復の面であまり不都合を感じることはないでしょう。しかし相手が無保険の場合や、年齢制限などで保険が適用されない場合、損害賠償の請求先や相手の支力などの面で、大きな問題が発生するケースが多々あります。
そんなとき、あなたを助けてくれるのが弁護士です。未成年者が相手の交通事故に遭い、その対応に困っているなら、交通事故の処理に詳しい弁護士に相談してみてください。
交通事故に強い【おすすめ】の弁護士に相談
交通事故一人で悩まずご相談を
- 保険会社の慰謝料提示額に納得がいかない
- 交通事故を起こした相手や保険会社とのやりとりに疲れた
- 交通事故が原因のケガ治療を相談したい