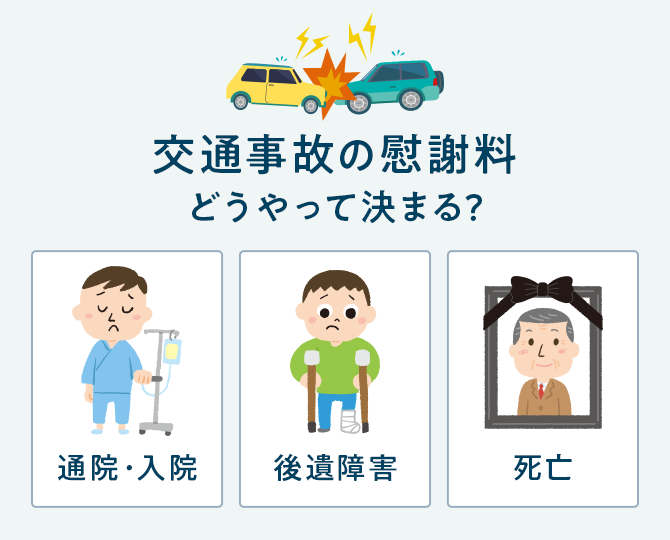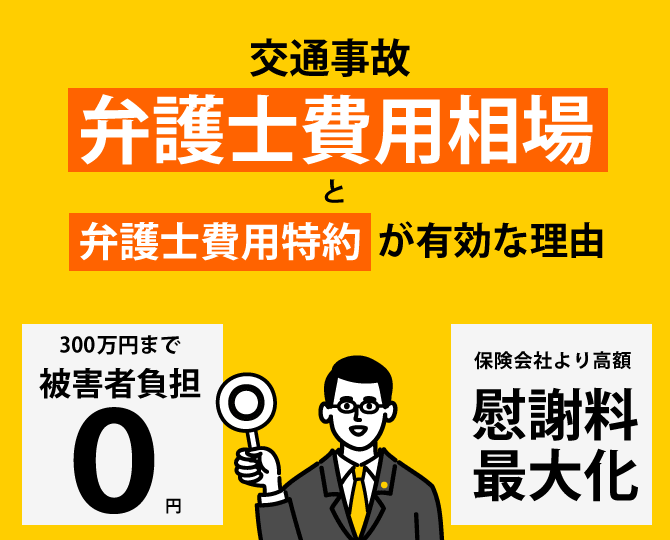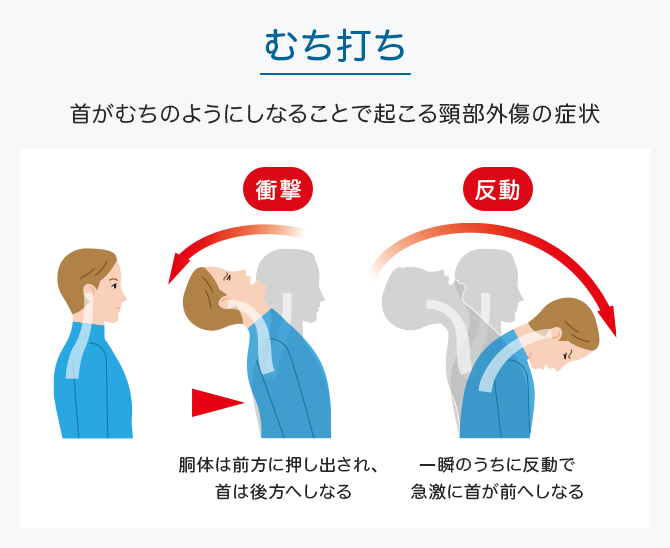交通事故の損害賠償は誰に請求できる?相手は加害者だけではない
- 監修記事
-


原則として、交通事故の損害賠償請求は被害者本人が加害者本人に行うもの。しかし、加害者に支払い能力がない場合や業務で運転していた時、加害者が未成年の際など、加害者以外の人へ請求すべきケースもあります。事案ごとの賠償金請求先をしっかり見極め、十分な損害賠償を受けましょう。
目次[非表示]
損害賠償請求の相手は原則として加害者本人
しかし使用者や運行供用者に範囲が広がるケースもある!
交通事故の被害者が損害賠償を請求できる相手は、原則として加害者本人または加害者が加入している任意保険会社です。
しかし事故の状況などにより、損害賠償を請求する相手が加害者以外の第三者を含めた複数になるケースもあります。
加害者本人が保険に未加入の場合、未成年で損害賠償を支払う財力がない場合などには、加害者本人から損害賠償金が被害者に支払われないリスクが高くなるでしょう。そういった場合でも法律などで規定された相手に損害賠償請求を行える可能性があります。
損害賠償義務を負う人の範囲は広い
まず、交通事故の損害賠償義務のある人を列挙します。
運転者
事故を起こした車を運転していた者(加害者)は、民法第709条に定められているとおり「他人の権利を侵害した不法行為者本人」として、損害賠償義務を負います。
民法第709条、不法行為による損害賠償
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
運転者が未成年であっても、責任を認識する能力である「責任能力」があるとされる場合(だいたい12~13歳以上の知能を有する場合)には、損害賠償義務があります。
使用者
使用者(雇用主)は、民法第715条第1項に定められているように、被用者(雇用されている者)が、仕事上において第三者に与えた損害を賠償する責任を負います。
従業員が交通事故を起こしたら、使用者が賠償責任を負う可能性があります。
民法第715条、使用者等の責任
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
運転者(加害者)が業務中に起こした事故については、使用者も運転者と連帯して損害賠償責任を負います。
運行供用者
交通事故の損害賠償請求は、事故による人身損害と物的損害に分けられます。
損害が大きくなる人身損害については、自動車損害賠償保障法第3条により「運行供用者」も加害者本人とともに損害賠償義務を負うと定められています。
物的損害については、運行供用者の損害賠償責任はありません。
自動車損害賠償保障法第3条、自動車損害賠償責任
自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときは、この限りでない。
運行供用者は「自己のために自動車の運行の用に供する者」です。具体的には以下のような人が運行供用者に該当する可能性があります。
- 事故を起こした自動車の所有者
- 事故を起こした自動車を貸した人
- 従業員が会社の車を運転し事故を起こした場合の会社
- レンタカーで事故が起こったときのレンタカー会社
- 子会社や下請け会社が、親会社または元請けに専属して(指揮監督権を持って)業務を行っている場合の親会社または元請け
- 子どもの自動車の維持費などを負担している親
上記の人は運行供用者に該当しますが、詳細には個別の判断が必要です。
裁判例や法律解釈を参考にする必要もあり、弁護士に相談して損害賠償の請求を行う方が良いでしょう。
交通事故に強い【おすすめ】の弁護士に相談
交通事故以下、運行供用者責任が発生する事例をパターン別にご紹介します。
加害者が運転していた車の持ち主に請求できるケース
人身事故を起こした車が加害者の所有物ではなかった場合、車の所有者に事故の損害賠償を求めることが可能になります。例えば、加害者が友人に車を借りていた場合、その友人が加害者に車を貸すことを許可していれば、車の所有者にも損害賠償請求できます。
持ち主と借り主の関係性も重要に
損害賠償の請求をすると、車の持ち主が「貸した覚えがない」と主張する可能性があります。持ち主と借り主(加害者)の関係性にもよりますが、無断で使用したとすれば窃盗罪が成立する可能性もあり、加害者側は損害賠償どころの話ではなくなるでしょう。賠償金請求の示談交渉は紛糾することが予想されます。
スムーズに車の持ち主への損害賠償請求を進めるには、法律に詳しい弁護士に交渉を依頼するよう強くおすすめします。
こちらも読まれていますレンタカーで事故にあったら保険の補償はどうなる? 自己負担の出るケースと正しい対処法まとめ レンタカーを借りて事故を起こした場合はレンタカー会社が加入している保険を使用するのが原則。...この記事を読む
加害者が運転していた車が、会社所有であった場合
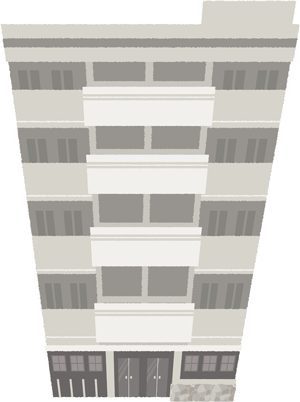 加害者が乗っていた車が会社所有の車であった場合、会社に運行供用者責任が認められ、被害者は会社にも損害賠償請求できます。加害者が仕事以外の目的、例えば旅行に行く時や引っ越しに会社の車を使用していたとしても、過去の判例では会社の運行供用者責任が認められています。
加害者が乗っていた車が会社所有の車であった場合、会社に運行供用者責任が認められ、被害者は会社にも損害賠償請求できます。加害者が仕事以外の目的、例えば旅行に行く時や引っ越しに会社の車を使用していたとしても、過去の判例では会社の運行供用者責任が認められています。
ただし従業員が会社に無断で乗り回していた場合には会社に責任が発生しない可能性があります。
使用者責任としての請求も可能だが…
加害者が仕事中に事故を起こした場合は、使用者責任として加害者の雇い主に対して損害賠償請求をすることも可能です。ただし使用者責任が成立するには「業務上の利用」でなければならず、プライベート目的であれば使用者責任は成立しません。また被害者側が加害者の過失を立証する必要があります。
人身事故で加害者の勤務先の会社に損害賠償請求するなら、使用者責任より運行供用者責任の方が、ハードルが低くなります。
事故の原因になった第三者や、道路の責任者に請求するケース
交通事故が起こったとしても、その事故原因は、必ずしも加害者だけにあるとは限りません。加害者が道路に飛び出してきた人を避けようとしてハンドルを切り損ねたなど、事故の本当の原因を作った第三者がいる場合もあります。
事故の原因を作った者に請求が可能
事故の原因を作った第三者にも不法行為が成立するので、損害賠償を請求できます。
また道路整備の不備で、路面のアスファルトに亀裂が入っていて、それが原因となって事故が発生したなら、道路の管理責任者である国や自治体も損害賠償請求の対象になります。
加害者が未成年の場合、監督責任のある親に請求できるのか?
交通事故の加害者が未成年であっても、12、13歳程度の事理弁識能力があれば損害賠償義務を負います。
しかし未成年者は自賠責保険や任意保険に加入していないケースも多く、本人にも資力がないケースがほとんどでしょう。本人に請求しても十分な賠償を受けられないリスクが高くなります。
親に損害賠償請求を行うのは簡単ではない
相手が未成年の場合、「加害者の親に損害賠償を請求できないか?」と考えがちですが、親への請求は認められるとは限りません。
未成年者に責任能力がない場合には親に監督者責任が発生しますが、未成年者自身に責任能力があれば親には当然には責任が発生しないためです。
子どもが12、13歳以上になっていたら、親には通常監督者責任が発生せず、必ずしも請求できません。
子どもが12,13歳以上になっても親に責任が発生するのは、親が未成年者による無免許運転を知りながら放置していたなど、親自身に不法行為が成立すると考えられる場合に限られます。
ただし親に運行供用者責任が発生すれば親へ賠償金を請求できます。
未成年が事故を起こしたときに親に請求できるかどうかについては、専門的な法的知識がないと判断が困難です。一般人にはかなり難しいので、弁護士に相談して責任追及してもらいましょう。
加害者以外に損害賠償請求が可能な相手は多い。しかし賠償金を取るのは大変!
以上のように、加害者以外にも損害賠償を請求可能な相手は多くいます。仮に加害者自身に損害賠償能力がなくても、請求先が増えれば資力のある方へ請求しましょう。
弁護士に依頼することが最善の策
実際には加害者以外の相手に請求を行ったからといって、簡単に賠償に応じてもらえるとは限りません。第三者に請求してもすんなり支払いを受けられなければ、交渉はこじれて決裂してしまうでしょう。
より確実に、スムーズに支払いを受けるには専門知識と交渉スキルを持った弁護士へ依頼すべきです。
加害者本人以外の相手に損害賠償を請求する場合は、交通事故に積極的に取り組んでいる弁護士に相談して、交渉を任せるのがベストな対応といえます。
交通事故に強い【おすすめ】の弁護士に相談
交通事故一人で悩まずご相談を
- 保険会社の慰謝料提示額に納得がいかない
- 交通事故を起こした相手や保険会社とのやりとりに疲れた
- 交通事故が原因のケガ治療を相談したい