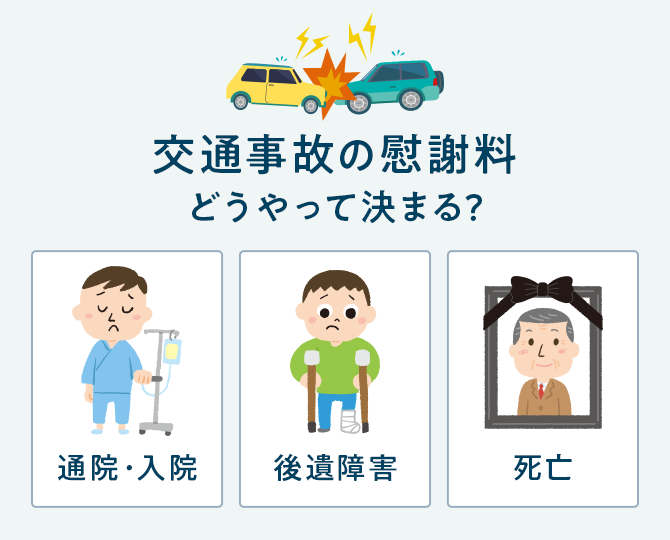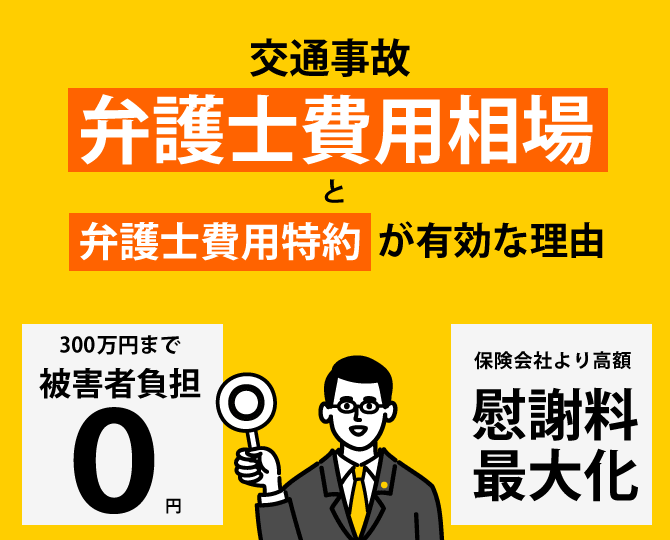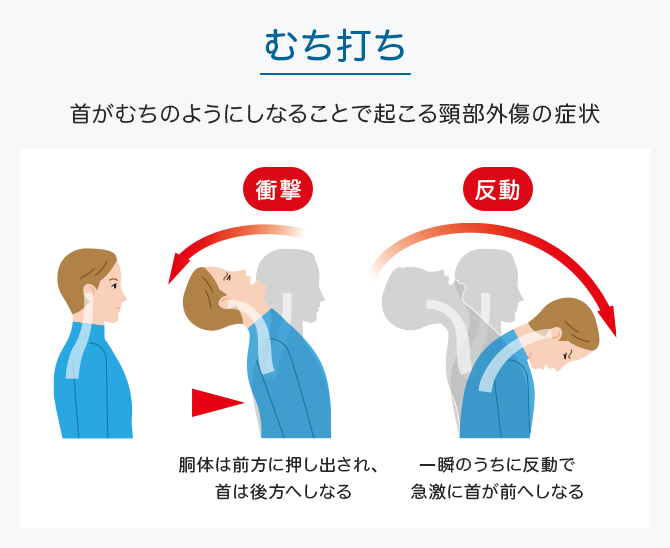後遺障害10級の主な症状と慰謝料相場を解説
- 監修記事
-

交通事故弁護士相談広場編集部
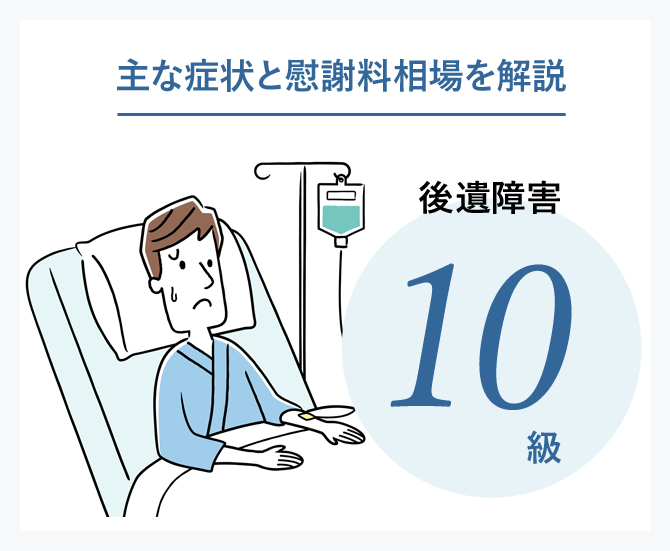
交通事故により後遺障害10級の症状が残ってしまうと、労働能力は27%失われます。健常者であった事故前と比べ73%しか働けなくなり、職場に復帰することも難しくなりがちです。
後遺障害の影響による減収は、逸失利益として加害者に請求することができますが、さらに慰謝料を請求することにより取得額を上乗せすることができます。
後遺障害を伴う交通事故に対する慰謝料請求の手続きを確実かつ効率的に行うには、専門家の力を借りるのが一番です。交通事故に強い弁護士に依頼して、被害の実状に適った十分な慰謝料を手に入れましょう。
こちらも読まれています交通事故の慰謝料相場はいくら?被害者がもらえる賠償金の計算方法 交通事故の慰謝料計算基準には3種類があり、中でももっとも高額なのは弁護士基準です。弁護士費用を払っても大きなおつりがくる...この記事を読む
目次[非表示]
後遺障害10級の認定基準~該当する症状は?
後遺障害の等級は、後遺障害の症状が最も重いものが第1級で、そこから軽くなるごとに級数の数が増え、最も軽い等級が第14級となります。
本項で説明する後遺障害第10級は、労働能力喪失率は第11級の20%に対し、27%と定められています。労働能力が健常者の73%しかないという重い後遺障害を背負ってしまった状態です。このような重い後遺障害が残ってしまうと、事故前と同じ仕事や作業をする際に、仕事内容によってはかなりの不便を感じ、元の仕事に復帰できないケースも考えられます。
後遺障害10級に該当する症状は、次の11種類です(自賠法施行令 別表二)。
| 1号 | 一眼の視力が〇・一以下になったもの |
|---|---|
| 2号 | 正面を見た場合に複視の症状を残すもの |
| 3号 | 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの |
| 4号 | 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
| 5号 | 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの |
| 6号 | 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの |
| 7号 | 一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの |
| 8号 | 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの |
| 9号 | 一足の第一の足指又は他の四の足指を失ったもの |
| 10号 | 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
| 11号 | 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
これらのいずれかの症状があれば、自賠責保険金の支払い請求と併せて、後遺障害10級の認定審査を受けることができます。
※後遺障害等級の認定審査は、後遺障害に対する自賠責保険金の支払い手続の中で行われます。(自賠法施行令2条1項3号ロ~へ)。
以下、各症状について具体的に説明します。
1号)一眼の視力が〇・一以下になったもの
交通事故により、片目の矯正視力が0.1以下になることをいいます。矯正視力とは、裸眼でなく、メガネやコンタクトレンズを着けたときの視力です。
交通事故に遭う前から片目の矯正視力が0.1以下だと、この認定は受けられません。ただ、事故前の片目の矯正視力が0.2以上であったことを証明するのは大変難しいことです。こうした事態に備え、普段から眼科で定期的に視力検査を受けておくのがよいでしょう。
なお、視力の測定は、万国式試視力表を用いるとされています。眼科での視力検査に使うもので、ランドルト環という円の切れ目や、アラビア数字・カタカナ・ひらがなを読み取る表のことです。(自賠法施行令別表 備考一)
2号)正面を見た場合に複視の症状を残すもの
複視とは、両目で見たときに同じ物が2つに見えることです。
乱視と似ていますが、片目で見たとき、複視なら物が1つしか見えないのに対し、乱視だとやはり何重にも見えるという違いがあります。原因も、複視が目の筋肉や神経のまひであるのに対し、乱視は角膜の丸みが失われることによる屈折異常です。
両目で正面を見て複視が起きれば10級に当たります。左右上下といった正面以外を見て複視が起きるのは13級の症状です。
3号)咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
交通事故により、顎の骨や筋肉、脳や神経に損傷を受けると、咀嚼障害や言語障害が残ることがあります。
咀嚼(そしゃく)とは、歯で食べ物を噛み砕いて食道へ送れる大きさや形にすることです。10級でいう咀嚼障害は、普通の食材は咀嚼できるが、歯ごたえのある堅いものを咀嚼できないことをいいます。
言語障害は、正しい発音ができない構音障害と、言葉を使うことができない失語症とに分けられます。10級でいう言語障害は構音障害のことで、次の4種類の発音のうち1種類の発音ができなくなることです。
- 口唇音(唇で発音。ぱ行音、ば行音、ふ、ま行音、わ行音)
- 歯舌音(歯や下で発音。さ行音、しゅ、し、ざ行音、じゅ、た行音、だ行音、な行音、ら行音)
- 口蓋音(上あごで発音。か行音、が行音、ぎゅ、にゅ、ひ、や行音、ん)
- 咽頭音(のどの奥で発音。は行音)
咀嚼障害と言語障害のどちらかが残れば10級、両方が残れば9級6号となります。
4号)十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
歯科補綴(ほてつ)とは、交通事故で歯が欠けたり無くなったりした部分を人工物で補うことをいいます。
人工物とは、クラウン(かぶせ物)・ブリッジ(架橋義歯)・部分入れ歯・総入れ歯・インプラント(人工歯根)・顎義歯(失った顎の骨を補う義歯)のことです。補綴後にホワイトニング(汚れたり変色した歯を白くする施術)をすることもあります。
事故発生後に歯科に行き歯科補綴を受けることで日常生活に不便はなくなっても、後遺障害として認められます。しかし、仕事上の不便が少ないことから逸失利益が認められにくくなるため、その分、慰謝料の増額を求めたいところです。
歯科補綴は5つの等級に出てきますが、補綴する歯の数により等級が分かれます。「親知らず」を除く永久歯の半分以上となる14歯以上なら10級、10歯以上で11級、7歯以上なら12級、5歯以上だと13級、そして3歯以上の14級といった分かれ方です。
5号)両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
交通事故によって、両耳の聴力が、1m以上離れた相手の普通の声が聴き取りにくくなるまでに低下することです。
数値でいうと、次のいずれかの状態を指します。
- 両耳でも50デシベル以上の音でないと聴き取れない(平均純音聴力レベルが50デシベル以上)
- 両耳でも40デシベル以上の音でないと聴き取れず(平均純音聴力レベルが40デシベル以上)、しかも「ア」「オ」などいくつかの言葉のうち7割以下しか聴き取れない(最高明瞭度が70%以下)
専門医である耳鼻科の医師に詳しい検査をしてもらうことが必要です。
6号)一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
交通事故により、片耳の聴力が、耳元での大声でないと聴き取れないまでに低下することをいいます。
数値でいえば、80デシベルから90デシベルに近い音でないと聴き取れない状態です。耳鼻科の医師による専門的検査が必要となります。
ただ、片耳の聴力がかなり低下した状態といえますので、片耳で音を聞き分けることが必要な仕事の場合、復職が難しくなるケースもあるでしょう。
7号)一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの
交通事故によって、片手の親指、または親指以外の2本の指について、その用を廃することです。
手指の「用を廃する」とは、指本来の働きができなくなることで、具体的には次のいずれかをいいます(自賠法施行令別表 備考三)。
- 指の第一関節から上の骨(末節骨)の半分以上を失う
- 指の付け根関節(MP関節)、親指以外の第二関節(PIP関節)、親指の第一関節(IP関節)の可動範囲が事故前の半分以下になる
8号)一下肢を三センチメートル以上短縮したもの
交通事故の衝撃によって、片脚が3cm以上短くなることをいいます。
片脚の短縮については、5cm以上なら8級、1cm以上であれば13級です。
片脚が短くなると、左右の脚の長さが異なって歩行に支障が出ることにより、労働能力の喪失につながります。
9号)一足の第一の足指又は他の四の足指を失ったもの
交通事故により、片足の親指、または親指以外の4本の指を失うことです。
足指を失うというのは、足指の付け根から先すべてを失うことをいいます(自賠法施行令別表 備考四)。指を失う足は左右いずれかの足です。
足指が失われたことは、医師はもちろん誰が見ても一目で分かるため、9号の認定を得ることはさほど難しくないといえるでしょう。
10号)一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
左右いずれかの上肢(肩口から指先まで)にある3大関節(肩・肘・手首)のうちの1つの関節に著しい障害が残ることをいいます。
「著しい障害」とは、関節の可動範囲が事故前の半分以下になることです。
関節がまったく動かなくなったり、可動範囲が事故前の1割以下になったりすれば、8級6号の「一関節の用を廃したもの」に該当します。
11号)一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
左右いずれかの下肢(股関節からつま先まで)にある3大関節(股・膝・足首)のうちの1つの関節に著しい障害が残ることです。
「著しい障害」とは、10号と同じく、関節の可動範囲が事故前の半分以下になることをいいます。
関節がまったく動かない、あるいは可動範囲が事故前の1割以下という状態になれば、8級7号の「一関節の用を廃したもの」として扱われます。
13級以上の後遺障害が複数ある場合、併合で等級は繰り上げに
これまで説明した1号から11号までのいずれかの症状があれば、後遺障害10級の認定を求めることが可能です。
そして、13級から9級の症状が2つ以上あれば、最も重い等級の1級上の等級へと認定が繰り上げられます(等級の併合。自賠法施行令2条1項3号二)。
たとえば、10級の症状が2つあれば併合9級に、10級と9級の症状が1つずつあれば併合8級となるわけです。
こうした等級の併合により、労働能力喪失率が、前者であれば27%から35%に、後者なら35%から45%に上がります。
労働能力喪失率が上がれば逸失利益が増え、損害賠償金の増額につながるのが、等級の併合が生み出すメリットのひとつです。
後遺障害10級の慰謝料の相場
自賠責基準による後遺障害10級の慰謝料相場
強制保険である自動車損害賠償責任保険(自賠責)では、国が定めた基準により、後遺障害10級の慰謝料は190万円(2020年3月31日までの事故は187万円)とされています。これが後遺障害の慰謝料についての自賠責基準です。
自賠責基準は、賠償実務において、10級その他の後遺障害による慰謝料額の最低水準として扱われています。
参考リンク:国土交通省WEBサイト「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準 第3の2(1)②」※PDFファイル
任意保険基準による後遺障害10級の慰謝料相場
後遺障害の慰謝料基準には、自賠責基準の他に、任意保険を扱う保険会社が個別に定める任意保険基準があります。
任意保険基準による慰謝料は、自賠責基準より少し高く、後述の弁護士(裁判)基準よりはるかに低い金額です。被害者の後遺障害の状態次第では、自賠責基準と同額の金額を提示してくる保険会社もあるとさえいわれています。
これまで任意保険基準は保険会社の内部情報として公にされてきませんでしたが、最近は任意保険基準をWEB上で公開している保険会社もあります。たとえば、損害保険ジャパン株式会社が定める後遺障害の慰謝料基準は、次の表のとおりです。
後遺障害者等級 父母・配偶者・子のいずれかがいる場合 左記以外 第1級 1,850万円 1,650万円 第2級 1,500万円 1,250万円 第3級 1,300万円 1,000万円 第4級 900万円 第5級 700万円 第6級 600万円 第7級 500万円 第8級 400万円 第9級 300万円 第10級 200万円 第11級 150万円 第12級 100万円 第13級 70万円 第14級 40万円
第10級の慰謝料は200万円で、自賠責基準の190万円より少し高く、次に紹介する弁護士基準よりずっと安いことが分かります。
弁護士基準(裁判基準)による後遺障害10級の慰謝料相場
交通事故の被害者となったとき、弁護士に加害者との慰謝料交渉を依頼すると、弁護士費用はかかりますが、もらえる慰謝料は通常、大幅に増加します。弁護士は弁護士基準(裁判基準)を基に慰謝料交渉を行うからです。
弁護士基準(裁判基準)とは、慰謝料の金額を判示した裁判例を基に算出された慰謝料額の目安です。
弁護士基準(裁判基準)は、日弁連交通事故相談センター東京支部が発行する「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称:赤い本)に掲載されています。「赤い本」によれば、弁護士基準(裁判基準)による後遺障害10級の慰謝料は550万円です。
| 自賠責基準 | 任意保険基準 | 弁護士基準(裁判基準) |
|---|---|---|
| 190万円 | 200万円 | 550万円 |
慰謝料交渉を弁護士に依頼したときとそうでないときとでは、もらえる慰謝料の額が約350万円の差があることがわかります。
これだけの差があれば、もらった慰謝料の中から弁護士費用を賄うことも十分に可能といえるでしょう。
これまでは弁護士への依頼というと敷居の高いイメージがありましたが、最近の弁護士事務所の中には、一般の人に分かりやすく弁護士費用の中身を明示したり、初回相談を無料で行ったりする所もあり、一般の人にとって弁護士への敷居は低くなりつつあります。
また、弁護士基準(裁判基準)による550万円という金額はいわゆる相場(通常の目安)であるため、交通事故に強い優秀な弁護士に依頼すれば、この金額以上の慰謝料をもらえる可能性も出てくるでしょう。
後遺障害10級の逸失利益の計算方法
後遺障害が残ると働くことが難しくなり、収入が減ってしまいます。こうした収入の減少は、事故に遭わなければ得られたであろう利益(逸失利益)として、加害者に請求することができます。
後遺障害による逸失利益は、平成13年に国が定めた支払基準により、次の式で計算することとされています。
“収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数“
参考リンク:国土交通省WEBサイト「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準 第3の1」※PDFファイル
後遺障害10級の逸失利益の労働能力喪失期間
労働能力喪失期間とは、後遺障害の影響により本来の仕事ができなくなるであろう将来の期間のことです。就労可能年数ともいわれます。
労働能力喪失期間は、前述の国の支払基準別表により、後遺障害等級が確定した時の年齢ごとに定められています。この別表では、年齢だけを基に労働能力喪失期間が定められていて、等級は問われていません。
参考リンク:国土交通省WEBサイト「就労可能年数とライプニッツ係数表」※PDFファイル
裁判では支払基準によらない逸失利益算定を求めることも可能
判例は、交通事故による逸失利益について裁判になった場合、裁判所は、支払基準に縛られることなく、労働能力の喪失率や喪失期間を認定できるとしています(最高裁判決平成18年3月30日)。
それぞれの争いにふさわしい解決をすることが裁判の目的であり、逸失利益の算定についても、支払基準といった一律の基準によるのでなく、個々のケースの実状に適った算定をするべきだからです。
被害者は、支払基準を超える労働能力の喪失率や喪失期間によって算定された逸失利益を、裁判によって加害者側に求めることができます。
実際に、10級の逸失利益が争われた裁判例を6つ紹介します。
| 判決年月日 | 年齢・性別 | 障害部位(号) | 労働能力喪失率 | 労働能力喪失期間 |
|---|---|---|---|---|
| ①最高裁 昭和48年11月16日 | 63歳 男 | 膝関節(11号) | 90%(27%) | 7年(11年) |
| ②大阪地裁 平成13年2月20日 | 50歳 男 | 上下肢関節(10号・11号=併合9級) | 27%(27%) | 4年(17年) |
| ③徳島地裁 平成24年1月18日 | 76歳 不明 | 左肩関節(10号) | 27%(27%) | 5年(6年) |
| ④大阪地裁 平成13年11月28日 | 46歳 不明 | 右手関節(10号) | 27%(27%) | 21年(21年) |
| ⑤大阪地裁 平成10年12月1日 | 28歳 男 | 右上肢関節(10号) | 27%(27%) | 39年(39年) |
| ⑥大阪地裁 平成11年12月2日 | 51歳 女 | 右足関節(10号) | 20%(27%) | 16年(16年) |
※( )内は支払基準での数値
④⑤を除き、支払基準とは異なる労働能力の喪失率や喪失期間が認定されていることが分かります。
その結果、逸失利益の額が、支払基準に従って計算した場合に比べて高くなる場合もあれば、反対に低くなる場合もあるといえるでしょう。
裁判所は支払基準も意識したうえで個別的な逸失利益を算定
前述の判例(最高裁判決平成18年3月30日)によれば、支払基準は、裁判に至らないケースについて、労働能力の喪失率や喪失期間を一律に定めることで、逸失利益を公平かつ迅速に算定し、保険金を速やかに支払うための決まりであるとされています。
裁判所は、逸失利益の算定に際して算定基準に縛られないとしても、自賠法16条の3という法律根拠を持つ算定基準を初めから無視するのではなく、ひとまず仮の基準として用いたうえで、算定結果がケースに妥当なら、それを逸失利益と認定し、反対に妥当でなければ、算定基準によらず、裁判所独自の判断で逸失利益を算定しているものと思われます。
裁判例④⑤は前者のプロセスにより支払基準に沿った判決となったもの、その他の裁判例は後者のプロセスで支払基準にしばられることなく実際の被害をふまえた逸失利益を裁判所が認めた事例といえるでしょう。
逸失利益がもらえない場合の原因
後遺障害10級が認められても、逸失利益がもらえないことがあります。代表的な3つの原因を紹介します。
交通事故に遭ったが収入は減らない
たとえばアパート経営者や年金生活者は、交通事故で後遺障害を負っても、事故前と同額の家賃や年金が入ってくるので、事故による収入の減少はないとされ、逸失利益はもらえません。
交通事故の前からもともと収入がない
たとえば年金がなく子どもの家に身を寄せている高齢者は、交通事故による後遺障害が認められても、事故前からもともと収入がなかったことから、事故による収入の減少ということが考えられないため、逸失利益はもらえないことになります。
交通事故に遭っても労働能力が下がらない
たとえば一日中パソコンに向かう仕事をしている人が、交通事故で片足の親指を失って10級9号の認定を受けても、仕事への影響は考えられないため、労働能力喪失率がゼロとなる結果、逸失利益もゼロになってしまいます。
後遺障害10級で障害者手帳はもらえる?
後遺障害10級で障害者手帳の取得は難しい
身体障害者手帳には医療費の助成、所得税・住民税の減額、鉄道・バスなど公共交通機関の運賃割引などいくつかのメリットがあるため、後遺障害10級の認定を受けたら身体障害者手帳ももらいたいところです。
ただ、後遺障害10級で身体障害者手帳をもらうのは難しいのが実状です。
障害者手帳取得には障害等級6級以上が必要
後遺障害10級で障害者手帳をもらうのが難しいのは、身体障害者障害程度等級表(障害等級)6級以上に該当しないからです。
障害者手帳をもらうには、7等級ある障害等級のうち6級以上に該当することが必要となります。しかし、後遺障害10級ではそれが難しいのです。
たとえば、両耳の聴力レベルでいえば、後遺障害10級5号で50デシベル以上(50デシベル以上の音でないと聴き取れない)とされているのに対し、障害等級6級では70デシベル以上(70デシベル以上の音でないと聴き取れない)とされています。後遺障害10級の人は50デシベルから69デシベルまでの音を聴き取れてしまうため、障害等級6級に該当しないことになってしまうわけです。
身体障害者障害程度等級表は、厚生労働省のWEBサイトで公開されています。
参考リンク:厚生労働省WEBサイト 「身体障害者手帳の概要 等級表」※PDFファイル
後遺障害10級認定を獲得するための重要なポイント
交通事故の被害者が後遺障害の認定を受けるには、事故直後から、医師に症状を正しく申告し、症状にふさわしい治療と検査を受け続けることが必要です。また、完治するしないに関わらず真面目に治療に取り組み、社会生活に復帰する努力を続ける姿勢を示すことも大切になってきます。
「複視」の症状を医師にしっかり伝えよう
交通事故によって同じものが2つに見えるようになると、「複視」と診断され、正面を見て複視が起きれば10級、正面以外の左右上下などを見て起きれば13級に該当します。
複視はこの2つの級にだけ当てはまる症状です。
複視の症状は、周りから見て分かるものでなく、被害者本人にしか分からないものなので、同じものが2つに見えることを医師にはっきりと伝えることが大切です。
正面をみて複視が起きることもはっきりと伝えましょう。あいまいな答えをして、左右上下など正面以外を見たときに複視が起きるというように医師に受け取られると、そのように診断書に記載されてしまい、13級の認定になってしまいます。
10級と13級とでは逸失利益や慰謝料の額が大きく違ってきますので、このことは、より高額な賠償金をもらうための大切なポイントです。
急性期を除き、信頼の置ける医師による治療を受けるべき
交通事故の後、後遺障害10級に当たる症状があれば、すぐに医療機関を受診するのが普通でしょう。
ただ、通院を続けても症状が改善しないと、もっと腕の良い医師を求めて他の医療機関を受診し、そこでも改善しないとさらに他の医療機関を受診するという、いわゆるドクターショッピングに陥る人が多いのも事実です。
最終的に信頼できる医師に巡り会えたとしても、事故から時間が経っているため、医師としても、症状が交通事故によるものかどうかの判断がつかず、後遺障害の診断書を書いてもらうことができなくなります。
交通事故後の受診先は、時間や交通事情などの面から通いやすく、信頼できる医師のいる医療機関を選ぶことが、指示どおりの通院を続け、症状固定となったら速やかに後遺障害診断書を書いてもらうためにとても大切なことです。
なお、救急搬送の場合だと、事故直後の急性期は救急隊が選んだ医療機関での治療となりますが、退院後は前述のような通いやすくて信頼できる医師のいる医療機関でフォローしてもらうようにしましょう。
咀嚼障害や言語障害を感じたら言語聴覚士のいる医療機関へ
交通事故に遭った後、歯で食べ物をしっかり噛み砕けない咀嚼障害や、正しい発音ができない言語障害を感じたら、言語聴覚士のいる医療機関を受診しましょう。こうした障害は、10級3号の後遺障害に当たります。
言語聴覚士とは、国家資格に基づき、話すことや食べることがうまくできない人への訓練その他の支援を行う専門職です。
医療機関では、咀嚼障害や言語障害のある患者さんに対して、医師だけでなく言語聴覚士も関わって、機能の改善に取り組みます。
症状固定の段階になると、医師は一緒に取り組んできた言語聴覚士の専門的意見を聞きながら、後遺障害診断書を作成します。言語や摂食の専門職である言語聴覚士の意見を反映させることで、患者さんの症状にふさわしい診断書の作成が可能になるわけです。それにより、被害の実状に適った等級認定へとつながることが期待できます。
こちらも読まれています後遺障害等級とは?認定を受けるまでの流れと等級一覧 交通事故に遭って辛い後遺症が残ってしまったら、「後遺障害等級認定」を受けて、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益などの補償を...この記事を読む
後遺障害診断書は、等級認定において非常に重要
後遺障害の等級認定審査は書類に基づいて行われますが、特に重要なのが医師の作成する後遺障害診断書です。
後遺障害の知識と経験豊かな医師を主治医に
審査に通り、希望する等級をもらえるだけの診断書となるかどうかは、作成する医師の後遺障害についての知識と経験が決め手となります。もしも医師を選べるのであれば、そうした知識と経験に富んだ医師に診てもらうようにしましょう。
真面目に診療に通って医師との関係を良好に
審査に通るだけの診断書を書こうという気持ちを医師に持たせることも重要です。それには、まず医師の指示どおりに真面目に診療に通いましょう。真面目に通ったにもかかわらず後遺障害が残ってしまったとなれば、医師としても、審査に通る診断書を書いてあげようという気持ちになるはずです。
後遺障害が残ることは、本人にはとても辛いことです。かといって、医師のやり方に文句を言ったり、真面目に診療に通おうとしない患者に対して、審査に通る診断書を書いてあげようと思う医師はまずいないと考えてよいでしょう。
後遺障害の認定率は、約5%という狭き門です。しかも認定審査で占める後遺障害診断書の重要性から考えれば、医師との良好な関係を保てるかどうかが認定を左右するといっても過言ではありません。
関節の可動範囲は自賠責保険の基準に則って測定を
片方の上肢または下肢にある3つの関節のうち、1つの関節の可動範囲が事故前の半分以下になれば、10級10号または11号に当たります。
自賠責保険が基準とする関節可動範囲の測定方法は、「関節可動域表示ならびに測定法」(1995年 日本整形外科学会・日本リハビリテーション医学会の共同作成)です。
この方法によらない関節可動範囲の測定は、被害の実態にそぐわない等級認定につながるおそれがあります。実際、これと異なる測定の仕方による数値を診断書に記載する医師がいるとの指摘がなされていることも事実です。
医師には「関節可動域表示ならびに測定法」に則った関節可動範囲の測定をお願いすることが重要です。
後遺障害10級の等級認定にデメリットはある?
治療費・休業損害が打ち切られ、無収入の期間ができる
後遺障害10級の認定にはデメリットもあります。
1つ目は、等級認定の条件である症状固定により、それまで加害者側の保険会社からもらえていた治療費と休業損害がもらえなくなることです。
症状固定は「これ以上治療を続けても改善が見込めない状態」ですので、治療費が打ち切りになるのは当然といえます。
症状固定前の休業損害に代わるのが、症状固定後の逸失利益です。ただ、逸失利益は示談成立後の支払いとなり、示談成立までには症状固定から通常6か月から10か月かかります。
症状固定から6か月から10か月の間、被害者の収入がゼロとなる期間が発生します。
申請を行っても認定が認められない場合がある
2つ目のデメリットは、申請しても認定が認められず逸失利益や慰謝料をもらえないケースがほとんどであることです。
後遺障害の等級審査を行う損害保険料率算定機構の2019年度の統計では、10級が認められた件数は1715件、認定件数全体の3.26%とされています。
全ての申請のうち、いずれかの等級が認められるのが5%であると言われています。
等級認定申請を行ったとしても、必ずしも認定が認められるものではなく、認められたとしても希望の等級にはならない可能性もある等、ハードルの高い手続きであるといえます。
手続き自体の時間と手間
3つ目のデメリットは、認定申請に時間と手間がかかることです。
後遺障害の等級認定を申請するには多くの書類をそろえなければならず、不慣れな被害者にとってかなりの手間暇がかかります。
特に重要な後遺障害診断書とそれに添付する検査結果や画像(MRI・CT・X線など)についても、医師が多忙な業務の合間で作成に取り組むため、ある程度の時間がかかるのは覚悟しなければなりません。
後遺障害等級認定を受けることそのものにデメリットはない
ただ、これらのデメリットは、認定手続を進める際に生ずるデメリットであり、等級認定を受けること自体のデメリットではありません。等級認定を受けることには、交通事故による被害にふさわしい逸失利益と慰謝料をもらえるという大きなメリットがあるのです。
そして、前述した
- 等級認定申請中の収入の確保
- 難関ともいえる等級認定の取得
- 認定手続の効率化
という手続上の問題を解決するには、まず弁護士に相談することが重要です。
特に、後遺障害等級認定にも精通した交通事故に強い弁護士に相談すれば、豊かな法律知識と実務経験を基に、有益なアドバイスと効果的な手続代行をしてもらえます。
後遺障害10級認定の申請を弁護士に依頼すると?
後遺障害10級をもらうには等級認定の申請をしなければなりません。こうした手続は普段から関わったことのない被害者にとっては大きな負担といえます。
後遺障害10級をもらえたとしても、10級の逸失利益や慰謝料は高額であることから、被害者側が示す示談内容に加害者側が素直に応ずることはないでしょう。
逆に、10級を基に加害者側の保険会社が示してくる逸失利益や慰謝料の額は、自賠法施行令別表や支払基準に定められた最低ラインの金額であることを覚悟しておきましょう。
交通事故の被害者が、弁護士の力を借りるべきもう一つの理由
交通事故の被害者となった場合、示談交渉の相手は、加害者が加入する保険会社の担当員であるのが普通です。
保険会社の交渉のプロを相手に、交渉に不慣れで、交通事故の賠償金相場さえ知らない被害者が自分に有利な条件を引き出すことは不可能に近いといってもよいでしょう。
そんなとき被害者の力強い味方になってくれるのが弁護士です。交通事故についての法律知識と実務経験を兼ね備えた専門職として、加害者側の保険会社との交渉においてその才を発揮してくれるでしょう。
弁護士に依頼するタイミングは交通事故に遭った直後がベストです。ただ、保険会社との交渉の中で提示された金額に納得がいかず弁護士への依頼を考えるケースもあります。そうした時点からでも遅くはないので、自分に有利な示談を進めるため、弁護士の活用をぜひ考えてみましょう。
まとめ
交通事故の後遺障害に対する慰謝料は、前述の通り、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準(裁判基準)によって大きく異なり、等級が1つ変わるだけで金額も大きく増減します。弁護士に相談すれば、認定を得るためだけでなく、等級を上げる方法をアドバイスしてくれることもあります。
10級の自賠責基準の慰謝料が190万円、弁護士基準(裁判基準)で550万円であるのに対し、11級の場合は自賠責基準で136万円、弁護士基準(裁判基準)で420万円と大きな開きがあるため、ぜひ10級の認定を取りたいところです。
10級の後遺障害の症状は、社会復帰が難しいとまではいかないにしろ、仕事の内容次第では元の職場に復帰することが難しい場合もあるでしょう。
交通事故の被害者となって後遺障害が残り、等級の認定や加害者側が示した慰謝料に不満があるときは、被害の実状に適った慰謝料をもらえるように、まず弁護士に相談することをお勧めします。
交通事故に強い【おすすめ】の弁護士に相談
交通事故一人で悩まずご相談を
- 保険会社の慰謝料提示額に納得がいかない
- 交通事故を起こした相手や保険会社とのやりとりに疲れた
- 交通事故が原因のケガ治療を相談したい