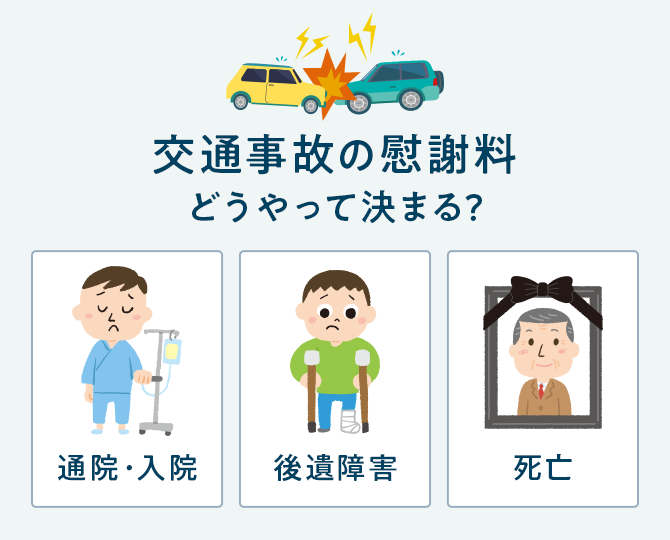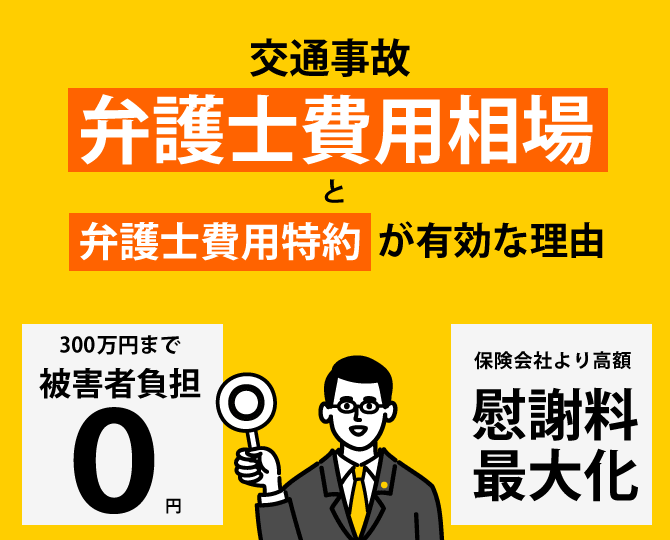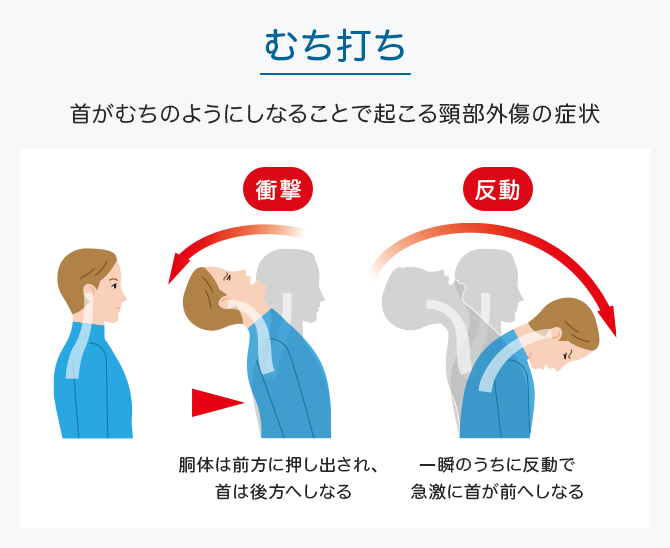交通事故の加害者に刑罰を与える方法はない?想定される刑事罰の内容と適用条件
- 監修記事
-

佐藤 學(元裁判官、元公証人、元法科大学院教授)

目次[非表示]
交通事故は「犯罪」
交通事故の被害に遭ったとき、加害者の対応に誠意が見られないので、被害者が憤りを感じることはよくあります。保険会社に対応を任せきりにしていて、一回も謝りに来ない加害者もいますし、死亡事故で葬式にも来ない加害者もいます。それどころか、自分の過失を小さくするために、嘘をついて被害者の過失を大きくしようとする加害者もいます。
このようなとき、加害者に刑罰を与えることができます。刑罰には、懲役、禁錮や罰金などがあります。交通事故の被害に遭ったら、加害者に対して「損害賠償請求」をすることができますが、これは、相手に対する罰ではありません。被害者が損害を受けているので、加害者に賠償をしてもらうだけの民事的な解決です。
そうではなく、加害者が悪質な交通事故を起こした場合には、国の捜査機関である検察官が起訴し、国の裁判機関である裁判所が加害者の処罰を決めることになります。これが、加害者に与えられる刑罰(刑事罰)です。交通事故は、犯罪として取り扱われるということです。
交通事故で成立する犯罪
それでは、交通事故の加害者には、どのような犯罪が成立する可能性があるのでしょうか?以下で、見てみましょう。
過失運転致死傷罪
最も基本となる交通事故の犯罪は、過失運転致死傷罪です(自動車運転死傷処罰法5条)。
過失運転致死傷罪は、自動車の運転者に要求される通常の注意を払わずに、交通事故によって人を死傷させた場合に成立します。例えば、脇見運転などの前方不注視や速度違反のため、被害車との衝突を回避できずに交通事故を起こし、被害者を死傷した場合に、加害者には過失運転致死傷罪が成立することになります。
過失運転致死傷罪の刑罰
その処罰としては、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金が科せられます。
かつて、通常の交通事故は自動車運転過失致死傷罪(旧刑法211条2項)、危険な運転に伴う交通事故は危険運転致死傷罪(旧刑法208条の2)で処罰されていたのですが、自動車運転による死傷事案についての実情や意見等に鑑み、事案の実態に即した罰則整備を行う必要性から、自動車運転死傷処罰法(自動車の運転による死傷事犯全般に対する罰則を内容とするもの)が成立、施行されたことにより、上記の自動車運転過失致死傷罪及び危険運転致死傷罪は削除され、それぞれを移す形で、自動車運転死傷処罰法に過失運転致死傷罪(5条)、危険運転致死傷罪(2条1号~5号)として規定されたのです。
危険運転致死傷罪
自動車運転死傷処罰法には、「危険運転致死傷罪」という犯罪類型も定められています(自動車運転死傷処罰法2条、3条)。
危険運転致死傷罪(2条)は、故意に一定の悪質で危険な運転行為を行い、その結果、人を死傷させた場合に成立する犯罪です。
例えば、
- 酩酊状態で運転していて交通事故を起こした場合
- 歩行者などが歩いているところに高速で突っ込んで人を死傷させた場合
- 高速度で信号無視をして事故を起こした場合
などに危険運転致死傷罪が成立します(自動車運転死傷処罰法2条)。
危険運転致死傷罪(3条)は、アルコールや薬物、又は病気の影響により正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、その結果、アルコールや薬物、又は病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた場合に成立します。
危険運転致死傷罪の刑罰
危険運転致死傷罪(2条)の処罰としては、人が怪我をしたのか死亡したのかで異なり、
- 人を負傷させた場合には15年以下の懲役
- 人を死亡させた場合には1年以上の有期懲役
がそれぞれ科せられます。
危険運転致死傷罪(3条)の処罰としては、人を負傷させた場合には12年以下の懲役、人を死亡させた場合には15年以下の懲役がそれぞれ科せられます。
過失傷害罪、過失致死罪、重過失致死傷罪
加害者が自転車運転者の場合、自動車運転死傷処罰法の適用はありません。また、免許制度がないため、基本的に業務上過失致死傷罪にも当たらないと考えられています。そこで、加害者が自転車運転者の場合、成立するのは「過失傷害罪」、「過失致死罪」か「重過失致死傷罪」です。
自転車運転者の過失の程度が、軽過失又は通常の過失であれば、被害者が、怪我の場合に過失傷害罪が成立し、死亡の場合に過失致死罪が成立します。
自転車運転者の過失の程度が、重大な過失であれば、被害者が死傷の場合に重過失致死傷罪が成立します。
過失傷害罪、過失致死罪、重過失致死傷罪の刑罰
その処罰としては、過失傷害罪については30万円以下の罰金又は科料 (刑法209条)、過失致死罪については50万円以下の罰金(刑法210条)、重過失致死傷罪については5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金がそれぞれ科せられます。科料というのは、1000円以上1万円未満の金銭の徴収を内容とする刑罰です(刑法17条)。罰金は、1万円以上とされていますので(刑法15条)、9999円までが科料になります。
物損事故では、犯罪は成立しない
交通事故には、人身事故と物損事故があります。物損事故とは、人が死傷せず、単に車、店舗、商品、塀、電柱などの物が損傷しただけの交通事故のことです。
交通事故の加害者が処罰されるのは、事故の結果、被害者を怪我させたり死亡させたりした場合のみです。物損事故では、加害者に刑罰を与えることはできません。
起訴する権限は検察官にしか認められない
以上のように、交通事故の加害者には、ケースに応じていろいろな犯罪が成立しますが、実際に刑罰を与えるためには、起訴され、加害者が「被告人」として裁かれることが必要です。そして、被告人とは、起訴された者です。
起訴ができるのは、検察官のみです。被害者は、起訴することができません。そのため、どんなに悪質な加害者でも、被害者が自分で加害者を刑事訴追することはできないのです。悪質な事案なら、被害者の処罰意思にかかわらず、検察官が起訴するでしょうが、通常一般の交通事故では、起訴されずに終わってしまうこともあります。
被害者ができる「刑事告訴」とは
それでは、被害者は、加害者に刑罰を与えるために、何もすることができないのでしょうか?
実は、被害者にもできることがあります。それは「告訴」です。告訴があると、捜査の端緒となって、捜査が開始され、被害者の告訴した人を、検察官が起訴することも考えられます。
告訴とは
告訴とは、被害者等の告訴権者が、捜査機関に対し、犯罪事実を申告し、かつ犯人の処罰を求める意思表示のことです。捜査機関とは、捜査を担当する国家機関をいい、司法警察職員、検察官、検察事務官がこれに当たりますが、告訴を受理できるのは、検察官又は司法警察員です。
刑事手続においては、被告人が有罪と認められる場合に、その者に対する的確な量刑とともに、被害者の心情に配慮すべき要請も、実現されるべきものです。検察官の起訴不起訴の処分の判断には、被害者の処罰意思が影響する事案もあるとされます。また、判決における量刑においては、被害感情も重要な要素と考えられており、被害者が加害者を宥恕している場合は、加害者に有利な情状になり、被害者が加害者の厳罰を求めている場合は、加害者に不利な情状になると解されています。
また、告訴があった事件については、「特に速やかに捜査を行うように努めること」とされ(犯罪捜査規範67条)、司法警察員は、告訴を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならないとされています (刑訴法242条)。
告訴できる人
告訴ができる人は、基本的には被害者本人です(刑訴法230条)。ただし、被害者に法定代理人(親権者・後見人)がいる場合には、法定代理人が告訴をすることができます(刑訴法231条1項)。例えば、子どもが交通事故に遭ったときには、親が告訴することができるということです。法定代理人は、被害者本人の意思に反しても告訴することが可能です。
被害者が死亡している場合には、被害者の配偶者、親、子ども、兄弟姉妹が告訴をすることができます(刑訴法231条2項本文)。ただし、被害者本人が、生前に「告訴をしない」という意思を明確にしていた場合には、告訴はできません(同項ただし書)。
被害者の法定代理人が被疑者になっているケースがあります。例えば、親が過失で子どもを轢いてしまった場合などです。この場合には、法定代理人以外の被害者の親族(配偶者、4親等以内の血族、3親等以内の姻族)に告訴権が認められます(刑訴法232条)。
親告罪とは
ところで、犯罪の類型には「親告罪」というものがあります。親告罪とは、公訴の提起に被害者等一定の者による告訴のあることを必要条件とする犯罪です。
先に紹介した交通事故関連の犯罪の場合、「過失傷害罪」のみが親告罪です。例えば、相手が運転する自転車で交通事故に遭い、怪我をした場合には、相手を告訴しないと処罰してもらうことができません。
これに対し、「過失致死罪」は親告罪ではありません。そこで、相手が運転する自転車で、被害者が死亡したケースでは、被害者の遺族が告訴しなくても、検察官が、その判断により、起訴する可能性があります。
告訴は取消しも可能
告訴をしても、その後いろいろな事情があって、気が変わることがあります。その場合、告訴は、公訴の提起があるまで取り消すことができます(刑訴法237条1項)。取り消すと、告訴はなかったことになるので、親告罪の場合には、加害者が起訴されることはなくなります。
これに対し、親告罪以外の罪の場合、告訴がなくても、検察官がその判断によって起訴することができるので、告訴の取消しがあっても、加害者が起訴される可能性は残ります。
告訴と告発の違い
告訴と似た制度に「告発」があります。この2つを混同している人も多いので、違いを確認しておきましょう。
告発とは、告訴権者以外の第三者が、捜査機関に対し、犯罪事実を申告し、かつ犯人の処罰を求める意思表示のことです。自分は被害を受けていないけれども、犯罪を見過ごすことはできないという場合に告発をします。また、告発があった事件については、「特に速やかに捜査を行うように努めること」とされ(犯罪捜査規範67条)、司法警察員は、告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならないとされています (刑訴法242条)。
ただし、告発の場合、被害者の処罰意思は告発状からは分からないので、加害者に対する処分内容に影響すると言えるかどうかは、事案によることになりましょう。告発の意義は、捜査機関が犯罪事実を把握できることです。どこかでこっそりと犯罪が行われた場合、目撃者が存在することがあります。被害者が死亡したり、被害者自身が被害届を出さなかったりすると、警察や検察は、被害があったことを知ることができません。そこで、第三者が告発をすることにより、捜査機関が犯罪事実を把握して、捜査を開始することができます。
被害届との違い
告訴は、被害届ともよく混同されるので、違いを説明します。
被害届は、被害者が捜査機関に対し、「犯罪の被害に遭った」ことを申告することです。告訴との違いは「処罰を求めているかどうか」です。告訴の場合には「加害者を処罰してほしい」という意思が明確になっています。これに対し、被害届の場合には、「単に被害があった」ということを申告しているだけで、加害者に対する処罰意思は明らかになりません。また、親告罪の場合には、被害届が出ているだけでは、検察官が起訴することはできません。
そこで、被害者として、どうしても加害者を処罰してほしい場合、できるだけ重い刑罰を与えてほしい場合には、被害届の提出だけでは十分でなく、告訴をすることが効果的な場合もあります。
刑事告訴する方法
告訴をするときには、以下の手順で進めます。
告訴状の作成
まずは、告訴状を作成しなければなりません。告訴状とは、加害者を処罰してほしいという意思を明確にした書類です。告訴は、検察官又は司法警察員に対して、書面で行うのが普通ですが、口頭で行ってもかまいません(刑訴法241条1項)。ただ、口頭の場合には、それを受けた者が告訴調書を作成しなければなりません(同条2項)。
告訴状には、犯罪事実が行われた日時、場所と犯罪事実の内容などを明らかにする必要があります(なお、犯人を特定して告訴するのが通常でしょうが、必ずしも犯人を特定してする必要はありません)。そのうえで、「犯人(加害者)を厳重に処罰してください」と記載します。
証拠を添えて提出する
告訴は、捜査の端緒にすぎないので、法文上、証拠を添えて提出することは求められていません。とは言え、捜査機関が、告訴に基づき、捜査を開始するためには、どのような証拠があるのかを把握している方が望ましいと言えます。その場合でも、証拠資料の標目や添付書類等の名称で足りるでしょう。
例えば、交通事故証明書や現場写真、被害者の受傷状況を示す書類(診断書や通院記録など)や発生した損害内容(治療費や葬儀費用の支払いに関する書類など)の標目等を記載すれば良いわけです。また、添付するとしても、コピーで構わないでしょう。
告訴状の受理
告訴によって捜査が開始されるためには、告訴が受理されるのが望ましいとは言えます。受理されなければ、告訴していないのと同じ扱いになってしまうからです。
しかし、各都道府県の警察では、「告訴・告発事件取扱要綱の制定について(例規通達)」に基づき、「告訴・告発事件取扱要綱の制定」がなされ、告訴・告発のあった事件については、原則、受理するものとされています。そして、その要綱においても、告訴状等に「添付された資料」の存在に触れた条項はあるものの、証拠の提出を求める趣旨、あるいは証拠の添付や提出を前提とする条項は見当たらないのです。
告訴状においては、犯罪事実を正確に、分かりやすく記載することは望ましいことでしょう。しかし、上記の要綱では、犯罪事実が一部不明瞭な告訴等についても、犯罪事実が概括的に特定されており、犯罪の嫌疑が認められれば、受理することとされています。
刑事告訴すると、必ず起訴されるのか?
被害者自身が相手を起訴することはできない
告訴があると、一般的に、捜査が開始されることになります。しかし、告訴があったからと言って、必ず加害者が起訴されるわけではないことには注意が必要です。
告訴は、被害者の犯人に対する処罰意思を明確にするものです。そして、被害者の犯人に対する処罰意思は、起訴不起訴の処分に影響する要素とは言えますが、最終的に起訴するかどうかを決めるのは、検察官です。検察官が、最終的に不起訴処分としてしまったら、被害者としてはいかんともし難いのです。
被害者は、検察審査会に申立てができる
ただし、被害者が、検察官の不起訴処分に不服がある場合には、検察審査会に審査の申立てができます(検察審査会法30条、2条2項)。
検察審査会は、衆議院議員の選挙権を有する20歳以上の者の中から、くじによって選ばれた11人の「検察審査員」(任期6か月)で組織されます。告訴や告発をした人が、検察官による不起訴処分を不服として検察審査会に申し立てると、審査会が開かれて、不起訴処分が妥当であったのかどうかを判断します。検察審査会が起訴相当の議決をしたときは、その議決書の謄本は、当該検察官を指揮監督する地方検察庁の検事正に送付されます。そして、検察官は、議決を参考にして捜査を遂げ、検討のうえ、起訴するかどうかを決めします。このとき、検察官は、起訴することも不起訴にすることも可能です。
起訴相当の議決に対し、なお、検察官がその事件につき不起訴処分をしたときは、検察審査会は再度その処分の当否を審査し、改めて起訴を相当と認めるときは、審査員8人以上の多数で起訴をすべき旨の議決をすることができます。これは「強制起訴制度」と呼ばれます。このとき起訴の手続きをとるのは、検察官ではなく、「指定弁護士」と言われる弁護士です。
加害者に対する刑事告訴後の流れ
加害者を告訴したら、どのような流れで捜査や裁判が進んでいくのか、確認しましょう。
捜査
捜査機関は、被害者の告訴を受理すると、捜査を開始することになります。そこで、捜査が開始されると、加害者を逮捕すべきかどうかが、まず問題になります。
逮捕と勾留
刑訴法は、逮捕について、通常逮捕、緊急逮捕及び現行犯逮捕の3種類を規定しています。以下では、通常逮捕を前提とします。
捜査の結果、「逮捕の理由」と「逮捕の必要」があれば、捜査機関は、被疑者を逮捕することができます。
被疑者は、逮捕されると、警察での取調べを受けます。通常は、逮捕から48時間以内に検察官に送致されます(刑訴法203条)。
そして、検察官は、事件の内容や証拠関係を検討するとともに、被疑者の身体の拘束を継続する必要があるかどうかを検討します。その結果、直ちに被疑者を起訴することができるのであれば起訴しますが、被疑者を取り調べるなどして、被疑者を拘束したままさらに捜査を行う必要があると判断した場合は、被疑者を受け取ってから24時間以内、かつ、逮捕から72時間以内に、裁判官に勾留の請求をします。検察官は、勾留請求も起訴もしないのであれば、直ちに被疑者を釈放しなければなりません(刑訴法205条)。
裁判官は、検察官の勾留請求を受け、勾留質問を行って、その当否を審査しますが、被疑者が、罪を犯した疑いがあり、住居不定、罪証隠滅のおそれ又は逃亡のおそれのいずれかに当たり、勾留の必要性があると判断した場合、10日間の拘束を認める勾留決定をします(刑訴法207条1項、60条1項、61条)。
検察官は、原則として、この10日間で起訴不起訴の判断をしなければなりませんが、やむを得ない事情がある場合は10日を上限として勾留の延長を裁判官に請求することができ、裁判官は、請求に理由があれば10日を上限として勾留の延長を決定することができます(刑訴法208条2項)。
このようにして、通常の犯罪については、最長で合計20日間の勾留が認められますが、それ以上の延長は許されておらず、検察官は、この期間内に起訴を行わない場合、直ちに被疑者を釈放しなければなりません(刑訴法208条)。
交通事故事件では、危険運転致死傷罪の場合はともかく、過失運転致死傷罪の容疑で逮捕された場合、住居不定、罪証隠滅のおそれ又は逃亡のおそれのいずれかに当たればともかく、被疑者は、勾留されずに、捜査機関側が任意に釈放しているのが一般的です。しかし、被疑者の犯した過失運転致死傷罪が、社会的耳目を集めた事件で、釈放されると世間の目に晒され、精神的に追い詰められて自殺するおそれがあるような場合(自殺自体、被疑者という証拠方法の隠滅であり、逃亡のおそれの最たるものという考え方が有力に主張されています)には、例外的に、逮捕後も勾留され、身柄拘束が続くこともあります。したがって、罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれが強ければともかく、一般的には、勾留が行われずに在宅捜査になっているのが現状のようです。
捜査
被疑者が身柄拘束をされている身柄事件であっても、在宅捜査になったとしても、捜査機関による捜査が続きます。
交通事故事件でも、被疑者の身柄は、上記のように、最大23日間拘束されることになります。
起訴又は不起訴の処分
検察官は、勾留期間が切れるまでに、起訴か不起訴の処分をするか、あるいは処分保留のまま釈放しなければなりません。
在宅捜査の場合、このような期間制限はありません。そこで、公訴時効が完成するまでの間に、起訴か不起訴かを決めれば良いことになります。交通事故事件では在宅捜査になることが多く、その場合には、捜査開始から起訴まで3か月以上かかることも普通のようです。
検察官が起訴したら、刑事裁判が始まります。不起訴処分は、検察官によるその事件についての終局処分ですが、裁判所の判決とは違って確定力はありません。したがって、後に新たな証拠が発見されるなど特別の事情が生じれば、不起訴処分を取り消して、その事件につき捜査を再開することは法律上可能です。
刑事裁判
被疑者は起訴されると、被告人という名称に変わります。そして、だいたい月に1回くらいのペースで審理が行われます。被告人が起訴内容を争っていない場合には、刑事裁判は2か月程度で終わります。被告人が事実関係を争っている場合(無罪を主張している場合など)には、刑事事件が長引いて、1年くらいかかることもあります。
判決言渡し
裁判で、必要な証拠の取調べや被告人質問などを終えると、裁判所は判決を言い渡し、被告人に対する刑罰の内容が決まります。宣告刑に執行猶予が付かない限り、被告人は刑務所に行かなければなりませんし、罰金となれば一定額の罰金銭が徴収されることになります。
被害者参加制度とは
被害者参加制度で、被害者も加害者の刑事裁判に参加できる
加害者が起訴され刑事裁判になった場合、被害者は、公判手続きの関与者と言えても、刑事訴訟の当事者ではありません。基本的に、証人としての役割しかありません。
しかし、これでは被害者保護にならないという批判があり、近年「被害者参加制度」という制度が作られました。被害者参加制度とは、一定の犯罪の被害者等や被害者の法定代理人が、裁判所の許可を得て、「被害者参加人」として刑事裁判に参加し、公判期日に出席するとともに、証人尋問、被告人質問等の一定の訴訟活動を自ら行うものです。被害者参加制度を利用できる犯罪は限定されていますが、過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪の場合、被害者が参加することが認められます。被害者参加制度を利用できるのは、被害者本人や法定代理人、遺族などです。
ただ、被害者参加制度を利用できる場合でも、必ずしも参加しなければならないわけではなく、参加するかしないかは、被害者が自由に選ぶことができます。
被害者参加制度を利用する方法
被害者参加制度を利用したい場合には、担当の検察官に、被害者参加を希望することを申し出ます。その後、検察官が、被害者参加を認めるべきかどうかの意見をて、裁判所に通知します。裁判所は、被告人又は弁護人の意見を聴き、犯罪の性質、被告人との関係その他の事情を考慮し、相当と認めるとき、被害者等の被告事件の手続きへの参加を許します。
裁判所が上記参加を許した場合、被害者や遺族などは、「被害者参加人」という立場で、被告事件の手続きに参加することができます。
被害者参加制度で、被害者に認められること
被害者参加制度を利用すると、被害者には以下のような権限が認められます。
| 出席権(刑事訴訟法316条の34) | 検察官席隣に着席して、加害者の刑事裁判に参加することができます。 |
|---|---|
| 検察官に対する意見表明権と検察官の説明義務 | 事件についての検察官の権限行使に関し、意見を述べ、検察官はその理由を説明しなければなりません。 |
| 証人尋問権(刑事訴訟法316条の36) | 裁判の証人に対し、加害者の情状に関する事項についての証人の供述の証明力を争うために必要な事項について、尋問することができます。 |
| 被告人質問権(刑事訴訟法316条の37) | 被告人に対し、質問をすることができます。被告人質問の内容は情状に関する事項に限られず、広くいろいろなことを聞くことが許されます。ただし、意見陳述をするために必要と認められる場合に限られます。 |
| 意見陳述権(刑事訴訟法316条の38) | 検察官による論告求刑の後、被害者自身が意見を述べて、求刑をすることが認められます。 |
被害者参加制度でも、弁護士に委託できる
被害者が、被害者参加制度を利用して加害者の刑事裁判に参加するとき、自分ひとりでは心細いことが多いことでしょう。意見を述べたり、証人尋問をしたり、被告人質問をしたりすることができるとは言っても、実際に何を聞いて良いのか分からないこともあるでしょう。裁判官、加害者本人や傍聴人の前で緊張してしまって、うまく言いたいことを言えない可能性もあります。
そこで、被害者参加制度を利用する場合、被害者は弁護士に委託することができます。被害者から委託を受けた弁護士が、参加を許された場合、被害者の代わりに、検察官の権限行使に関し意見を述べたり、証人尋問や被告人質問をしたりしてくれるので、被害者は安心です。被害者が自分で証人尋問や被告人質問をするときにも、必要なアドバイスを受けられるので、適切に手続きを進めることができます。
示談すると、刑が軽くなる
被害者が、加害者になるべく重い刑罰を与えたい場合、示談成立時期に注意が必要です。刑事事件では、示談が成立すると、加害者への処分が軽くなってしまうからです。
加害者をどうしても起訴してほしい場合や、加害者に重い刑罰を与えてほしい場合に、示談が成立すると、その事情は加害者に有利な情状となるため、起訴するか否かや判決の量刑に影響することは否定できません。加害者に厳罰を与えたいなら、加害者の刑事裁判が終わるまで、示談をしない方が望みがかなえられると言えましょう。しかし、そうした場合、加害者との示談が難しくなることも、考慮に入れておかなければなりません。
以上のように、被害者が加害者に厳罰を与えたい場合、まず告訴することも、一つの方法と言えます。告訴の手続きも、弁護士に依頼することができます。交通事故に遭い、加害者を許せないという感情を抱いているなら、冷静さを欠くことも心配されるため、加害者側と示談すべきか、起訴不起訴の処分や刑事裁判の手続きにどうかかわるべきかも含め、今後どのように対処すべきかについて、まずは交通事故や刑事事件に強い弁護士に相談してみることをおすすめします。
交通事故に強い【おすすめ】の弁護士に相談
交通事故一人で悩まずご相談を
- 保険会社の慰謝料提示額に納得がいかない
- 交通事故を起こした相手や保険会社とのやりとりに疲れた
- 交通事故が原因のケガ治療を相談したい